イシノラボ/マスターズ店長の連載
第1弾 日本オーディオ史
第14回 発売後の結果と評判、次の戦略
営業部からは順調にお店に買って貰っているとの連絡は入った。しかし、オーディオが全盛の当時であったから、ライバル機種も相当頑張っていたと思う。少しでも側面援助が出来ないかと、丁度、その時期にステレオサウンド社から別冊”サンスイ”が発売になった。AU−607/707が紙面の中心になったので、オーディオファンへの告知効果はあったと思う。この特集はラックス、ビクター、マランツとかのブランド特集本が時期を見て発売されていた。FM誌関係の紹介記事も多く出るようになったし、オーディオ誌への広告もそれなりに出していた。そのような販促活動のヘルプに11月、12月には明け暮れてしまった。本来業務ではなかったが、社外の状況を知り、今後の自分なりの方向と刷り合わせとか、修正とか、ヒントを得たかったのであった。
1976年が暮れて、1977年の正月を迎えた。これまたあたふたして、15日過ぎになって、電子機械工業会(EIAJ)の売上統計情報が入ってきた。結果は確かな手ごたえで、シャアーは記憶がさだかでないが、トップかトップに迫るところが11、12月の実績であった。上司は朝礼で”お客様のサンスイアンプへの信頼は厚い”と言って、関係者をねぎらうことはなかった。しかし、自分たちが頑張ってそうなったような言動をすれば、会社の中での反発、ジェラシーは強くなるだけであった。日本のサラリーマン社会は特にそうだ。謙虚に振るまえばますます、今後はやりやすくなるとの上司の他部門への配慮があったのだ。実際、製品を作ろうとも、企業の総合力で成し遂げるであって、このことはずっとその後、スピンアウトして、会社を設立して、自分たちで作ってみて、つくづく身浸みて、感じ取った。特に表に出ない、品質保証、生産技術、などの部門を軽んずるとメーカーはいつかは危なくなる。
金田明彦氏にお会いしたこと
DCアンプの具体化はアマチュアの方のほうが早かった。MJ誌編集の仲介でDCアンプ(金田アンプ)で実績のあった金田明彦氏(当時も秋田大の先生)にお会いすることが出来た。DCアンプの基本的なことを厳密な述べておられたのが記憶に残っている。例えば電源回路で、前段のデカップル回路もDC領域まで時間遅れなくすべきと述べたと思う。当時はそれほど印象は強くなかったが、それから長い年月が経って、金田氏は充分に実績をMJ誌で示し、それをまとめた書籍を私は買い求めた。序文に音楽について、その愛好度について書かれているのを読んで、改めて素晴らしい方だと思った。そう思うまでに20年以上の時の流れがあった。
アメリカオーディオ界への投入
日本で一応ヒットしたので、これらのアンプを海外で勝負するべきと思った。海外営業部では、海外、とりわけアメリカはレシーバーが一般的、本格的なものはセパレート(プリ、パワーアンプと別々)システムであって、プリメインアンプはアメリカでは馴染みの少ないアンプだったのだ。(現在でもアメリカ製のプリメインアンプは少ない。JBLプリメインSA−600は本国より日本で売れたと思う。)
それでも、何とかアメリカサイドでは売ってみようということになった。アメリカで売るとなるとULという安全規格(PSEより厳しい)を取得しないと売れないので、その取得費用は当時はアメリカまでサンプル、主要部品を送っておこなうので(現在では日本の会社で代行取得業務をおこなっている、)当時では¥50万/機種くらいかかっていた。それも取得して、海外ではAU−707のみ売ることになって、モデル名はAU−717となった。丁度、アメリカでの新製品発表会時期にアメリカに出張出来ることになった。シカゴでのCESで発表したあと、さらに、NY、SF、LAなどの主要都市で地区のサンスイのレップ(販売代理人)、主要販売店などをホテルに呼んで、内覧会を開くのであった。
やはり、アメリカはレシーバーマーケットであって、AU−717は評判は良くても、実販売となると多くは望めなそうであった。しかし、現地のLA責任者で(後のavex創業者でもあった)TY氏もやはりデザインの良さを認めて、強力な販売をおこなってくれた。予定数は充分消化できたが、利益は予定以下ではなかったかと今でもそう思っている。 ライバルブランドを見渡しても、プリメインアンプはCESでは見かけず、レシーバーか、レシーバーにスピーカー、レコードプレーヤー、カセットデッキを組み合わせたシステム(ワンブランド・システムと言う)がほとんどであった。日本製に対抗していたのはフィッシャーくらいで、スコット、シャーウッドなどの老舗は日本ブランド攻勢で弱体化していた。この時期、韓国、中国ではまったく工業製品の対米輸出はなかった時代だった。
ワンブランド用スピーカーは輸送費がかさむので、アメリカ現地で組み立てた安いものが多かった。なぜ、安く作れるか?それは黒人やヒスパニック系の労働者を使うので、工賃が安上がりなのである。アメリカ社会は今なお、格差、差別社会なのである。いろんな人種、民族が同じ地域に暮らすことは絶対無く、それぞれ分住しているのである。このときの為替レートは1$=¥308になっていた。その後に¥240くらいの円高になってきていた。
次への戦略
AU−607/707でうまく滑り出しても所詮は中級機で挽回したに過ぎない。まだ、かってのAU−9500のような上級機種ではまだ下位に甘んじていたのであった。”次はAU−907だな!”、どうするか?このままの延長上ではだめ、すなわち、下位から上級機種を作ってもイメージが上がらないのである。
まず、回路的な面から眺めると、先進のDCアンプであるには違いないが、初段はこれでかまわない、3段目の差動プッシュプル回路も悪くない、となると2段目の差動回路が平凡であるし、マイナス側へのシグナルの導き方がどうしても、レベルシフト回路を使用して、マイナス側の差動プッシュプルに導くのはスマートではないし、エレガントでもないし、立ち上がり(スルーレート)特性の障害にもなっていそうであった。ちなみにAU−607/707のスルーレートは60V/μsでかなり高いほうであった。
もやもやしているうちに原回路開発者のT氏に相談を持ちかけた。”どうも、2段目がすっきりしない、やはり、2段増幅回路がよいのでは!”と挑発的に言ってみた。技術部門のあるところではヤマハの2段差動回路を評価していたのを知っていた。”ともかく、レベルシフト回路がなくなるような回路が出来ないか?”、分かった!それではやってみよう。丁度、君と同期入社のTT君を回路開発に振り向けよう。T氏は研究開発部長になったので、専任で回路開発には取り組みことは出来ないが、協力すると言ってくれた。同期のTT君(今でも付き合いあるが、)は若く、クレバー、努力家であった。サービス部から開発部門に来て、意欲はまんまんであった。
また、ひずみ特性も0.03%ではなく、0.01%は切りたかった。どうしても、20kHzではトランスジスタの特性がネックになって、ここが障害になっていた。
無理すれば、発振安定度が悪くなって、市場クレームが多くなって、信頼感がなくなってしまう。AU−907の想定していたスペックは次のようなものだった。
| パワーアンプ部 | |
|---|---|
| 最大出力 | 100W+100W(8Ω) |
| 最低負荷 | 4Ω |
| ひずみ | 0.0081%以下(20−20KHz/8Ω/100W/2ch同時動作) |
| 周波数特性 | 10〜100KHz(−3db以内、1W/8Ω/2ch同時動作) |
| 入力感度 | 1V/47KΩ |
| スルーレート | 100V/μs以上 |
改良新デバイスの出現
バイポーラートランジスタの性能限界が見えてきた。そこで半導体各社は少数キャリアの蓄積効果によるスイッチングひずみ発生欠点を改良しようとしていた。具体的には富士通のリングエミッタトランジスタが始まりだった。エミッタを形状リング状にして、上記欠点を改善するものであった。また、サンケンではリニアアンプトランジスタ(LAPT)と称して、マルチエミッタ構造にして、改良してきた。これらの改良デバイスは確かに特性は良くなっていたが、やや大電流に対して弱くなるようであった。あまり無理が利かず、無理な使い方をすると破壊しやすかった。このことは次回でもう少し深めるつもりだ。
ケミコンと音質との相関とは
部品の音質傾向については1975年くらいまで、ほとんどメーカーは気を使っていなかった。電気的な特性については安全性、信頼性に関係するので、かなりの精度で知識は得られていた。例えば、コンデンサの高周波特性、漏れ電流、容量誤差、温度特性などなど。わたしもスピーカー設計の経験から、ほとんど音質傾向はスピーカーが支配的と思っていた。確かにスピーカーが再生音の傾向を決めることは今でもそうだが、その先に音質細部になると、部品が音質傾向を握ってくるようなことは、最初、ブロックケミコンで、自分として音質傾向をもつことは確認した。当時はケミコンブランド、仕様については、価格・納期などが優先していた。
ケミコンはアルミ箔の表面積を大きくすれば、その分静電容量を増すことが出来る。まずは小型化にするために、アルミ箔に酸化膜を作るとともに、エッチングと称する工程で、表面にでこぼこを作って広くするのである。現在はこの当時に比べ、3倍くらいの容量が出来て小型化に貢献している。ケミコンの品質、技術水準では日本(日ケミ、日コン)は世界一だと思う。そのあおりを受けて、スプラーグは一時ニッケミの傘下に(現在はフランスビシェーグループ)、マロリーはブランドは残っているが、コーネルタブラーに吸収されている。13回で述べた評論家K氏がいち早く、ケミコンによる音質個性を指摘していた。各社、オーディオ用ブロックケミコンの開発がアクティブになってきた。各社から、いろいろの試作品が次々と届く、そのうち、ケミコン工場に来て、生産現場を見れくれという誘いがあって、日コンの豊科工場を訪問したことがあった。なるほど、ケミコン作りは大量の電力、水を使う産業であることがわかった。小型のコンデンサは当時から自動機で超大量に作られていた。ブロックケミコンはまだ一部手巻でアルミ箔を巻いていた。
ブロックケミコンの音質にかかわるファクターはわたしは以下のように推測している。
- エッチング倍率
- 電極取り出しタブの本数、幅
- アルミ箔巻取テンション
- 層間紙
- 電解液
- 端子材質
- 充填量と材質
- (アルミ)外箱
ケミコンの専門家からは、もっとあるよ!と言われそうであるが。
エッチングゼロのアルミ箔をプレーン箔と呼ぶ。この箔で作ったケミコンは今でも持っているが、現在の技術では50V/3300μ入るであろうものが、プレーン箔であると50V/15μしか容量がとれない。音質は確かにきれいでピュアである。ケミコンメーカーはニーズが少ないのですぐ製造をやめてしまった。電極引出タブ数は多くすると手間を食う分、抵抗分が減り、音質も良くなろうが、コストとの兼ね合いもあった。巻き取りテンションは今は自動機でやっているので、いったん設定すれば均一である。試作品では手巻であるから、量産とでは音質が異なる場合もあった。層間紙はノウハウのかたまりらしく、マニラ麻、和紙、竹繊維、カーボン紙(ブラックゲート)、などいろいろあるらしい。電解液はうなぎ蒲焼のたれみたいな用液で導電性が物凄く、少しでもこぼして電位をかけると、通電する。電解液が漏れ出して、その付近がショートして事故になることがごくまれにあった(中国製ではまだあるらしい)。
電解液の経年変化で硬化したり、ガス化して、少なくなるとライフを終えるといううが、メーカーがいうより、そのライフはオーディオに関しては持つ。これは修理してみて、分かったことである。30年経っていても健在である。(但し、ガス化が著しく、膨らんでるものは交換時期である。)
音質との関連は各社ノウハウがあって、今でも公開できないであろうが、当時のケミコン会社は試聴室を作って、JBL4343を備えていた。そして、そこで聴いてみて、オーディオメーカーにサンプルを持参して、評価して貰う。そうして、採用をプッシュする営業であった。
音質にとって良さそうなことは、エッチング倍率は低いほうが良さそうである。前述のプレーン箔のケミコンはイシノラボでも販売しているので、その音質を確かめることも出来る。引出タブは太く(通常は6mmくらい)すると、これも良さそうであるし、引出タブ数が多いと良い方向である。また、ケミコンは整流時、またオーディオ信号で変調かけられて振動する。聴診器で聴けば、音楽が聴こえるはずである。
従って、ケミコンユニットを固定する充填材はいっぱい詰めたほうが良い方向であった。さらに、外側のケースは円柱であるが、フィリップスはこのケースに大きな凹凸をつけたケミコンを今でも作っているはずである。こうすると、強度が増して、ケミコンの振動抑制に有効とのことである。フィリップスのパテントであるらしい。
さて、AU−907(仮称)に搭載するブロックケミコンはどうしようかと思案していた頃にユニークな形状のケミコンを提案してきたメーカーがあった。次回をお楽しみに。
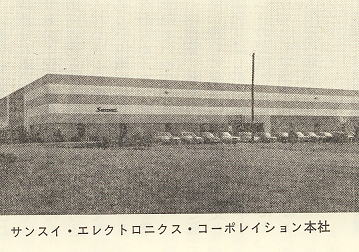
当時のアメリカ山水の広大な本社・倉庫(NJ州にあった。)
(特別にサンスイOBサイト支配人様に掲載許可をいただきました。)
2006年5月23日掲載