イシノラボ/マスターズ店長の連載
第1弾 日本オーディオ史
第57回 プロ用CTSブランド パワーアンプを開発するが失敗する
開発のきっかけ
(株)CTSの経営もやっと軌道に乗ってきて、懸案の自社ブランドのスタジオ用パワーアンプを製品化したいという目標が、具体化できるようになったと考えるようになってきた。
基本的回路構成は、(株)CTSを設立するときパテントを出願しておいたので、このパテント技術を使いたかった。だが、この技術ではパワーが出過ぎて(1kW/8Ω)しまい、採用できなかった。2013年の今なら、マッチングトランスを採用して500W程度に下げて、使いやすいアンプに仕上げることが可能であった。当時は直結回路であるべきという観念にとらわれていた。
やむなく、通常の回路で優れたサウンドが出るスタジオ用パワーアンプを開発することに軌道修正した。
仕様は以下のようにした。
- モノラル仕様
- 定格出力:400W(8Ω),700W(4Ω)
- 入力:バランス入力
- 入力感度:+4dBにおいて400W(32dBゲイン)
- 放熱方法:温度上昇時空冷ファンが動作
- 外形:EIA19インチラックサイズ,高さ:4U
重さには特に制限を設けなかった。外観・構造設計等の機構設計は、CTSに入社した若手の機構設計者のK君が担当して、なかなか格好良いものができそうであった。
電気設計は、サンスイを離れて高級カセットで名声高いN社に転職し、N社から(株)CTSに入社したK・K君が担当することにした。私は当時、(株)CTSの専務として経営、外部からの仕事の獲得、技術部門の全体統括をおこなっていたので、設計担当にはならなかった。K・K君はサンスイ当時、AU−D607X(Xバランス搭載)の電気設計を担当したので、私とはツーカーの間柄であった。私は(株)CTSのプロ用アンプ開発のプロジェクトリーダーのような役割を演じることになった。
一番問題になるのは、開発しても実際に売れるかどうかであった。当時の日本はバブルの真っただ中であったが、やや陰りが出ていて、午後3時の太陽の位置と言われていた。日が暮れるのにはそう時間はない、すなわち、バブルが崩壊するという懸念はあった。
また、当時のプロオーディオ業界はデジタルオーディオが本格化して、マルチチャンネルのアナログテープレコーダーは必要なくなり、プロ用デジタルレコーダー(三菱,SONY,サウンドストリーム等)が出現して、アナログ時代より簡単にレコーディングできる時代となっていた。すなわち、レコーディングスタジオの仕事が急激に減ってきたのであった。
この傾向はアメリカでも同様に始まりつつあった。
そのような状況下でも、何とか世に出そうと言う信念でこのプロジェクトを邁進させた。
いずれにしても、国内のレコーディング業界は相変わらず舶来主義で、国産のプロ用機材はまず採用されなかった。唯一、レイオーディオ(パイオニアOBの木下さんが興したプロ用大型スピーカーシステム)だけはレコーディングスタジオに設置されていた。
コンソールはイギリス製のフルデジタルコンソールSSL(ソリッド・ステート・ロジック)だけが多くのスタジオに争って納入されていた。デジタルオーディオ時代に乗り遅れまいと浮足立っていた。
従って、ニューブランドであるCTSアンプが採用される可能性はまず考えらなかった。
唯一、チャンスがあるとすれば、海外、とりわけアメリカで評判を取り、どこかのスタジオで採用してくれれば、その評判が国内に投影して売れる可能性があった。この状況は、現在の音楽界でも、海外コンクールで入賞すれば、評判となって仕事にありつけるということと同じであった。
成功確率は小さいが、開発するチャンスはCTSの財務状態では、当時しかなかった。
開発は進み、完成し、海外に売り込む
回路はポピュラーな2段差動、DCアンプとした。新回路で作りたかったが、輸出して海外で故障するとなるとサービスが大変であるから、なるべく実績のある回路とした。
技術者の使う時間が惜しいので、試作を順調に進め、2か月程度で2台の試作機ができ上がった。性能も安定しており、出てくるサウンドを知り合いのスタジオでヒアリングしてみたが、なかなかのパフォーマンスであった。
でき上がっても、そのままにしては何も起こらない。やはり、海外、アメリカで売り込もうということで、アメリカサンスイOBのI・FさんがNJに住んで、自営形態で会社を作っているので、コンタクトを取り、お話したところ、ちょうど日本の、ガラスキャビネットに入れたスピーカーシステム(佐々木硝子)をアメリカで売り出すところだから、オーディオビジネスとして活動できるというアクティブな状況なので、わたりに船とばかり、I・Fさんのプロモーション活動をしてもらおうということで話が進んだ。
タイミング的にラスベガスのWCES開催中が良かろうということで、急きょ、佐々木硝子で上述のスピーカーを開発しているHさんと一緒に渡米することになった。問題は重いパワーアンプサンプルをどう運ぶ?ということであった。航空チケットは格安のエコノミーであったから、心配であった。成田のANAカウンターで何とか頼み込んで、無料の手荷物として運べることになった。LAに着いたら、I・Fさんがミニバンのレンターカーを借りてくれていたので、積み込み、Hさんを含んだ3人で車でラスベガスを目指し6時間のドライブでラスベガスに到着し、プライベート展示するホテルにチェックインできた。
資金があればWCES会場にブースを構えることになるが、そうもいかず、WCES会場近くのホテルにお客さんを招いて、説明し、デモして、売り込む活動する新規進出するブランドはけっこうあった。
そして、WCESは開催された。I・Fさんはユダヤ系のアメリカ人を共同のかたちでアメリカでのオーディオビジネスをおこなおうとしていたから、I・Fさん、ユダヤ系のアメリカ人の人脈でお客さんを呼ぶことができた。
やはり、アメリカのデジタルオーディオ化が本格的になってから、レコーディングスタジオの経営は大変で、なかなか新規にパワーアンプを買ってくれるようなスタジオは見つからなかった。
DAVID MANLEYに出会う
なかなか売れそうなお客さんが来ないので、ややがっかりしていると、やかましい声が聞こえた。振り返ると、白人の老人が来ていた。挨拶を交わし、名刺のやり取りをすると、その老人の名刺にはVTL(バキューム・チューブ・ロジック)社長、DAVID MANLEYとあった。彼はプロオーディオ業界では有名で、イギリス生まれで、コンソールで有名なNEVE(ニーブ)社に勤務して、真空管アンプの設計者として名をはせたエンジニアであった。その後、南アで自分の会社を作り活動していたが、8年くらい前にアメリカに移住し、VTLを創立して、真空管アンプを作り、息子(LUKE MANLEY)とともに販売しているということであった。VTLの真空管パワーアンプが無骨でデザインがださく、日本では代理店のなり手がなかった(帰国して、菅野沖彦さんから聞いた)と聞いていた。
彼の一方的な話によれば、南アの国境沿いの隣の国で、大規模なレコーディングスタジオを建設すると言う。このスタジオはいくつものスタジオがあるので、必要なパワーアンプは10台以上になると言う。“お前が判断して、販売したいなら、おれが口を聞いても良いぞ!”という話であった。MANLEYの真空管アンプは真空管アンプなので、買ってくれないとのことであった。魅力的な話であったが、アメリカではなくアフリカ大陸となるとまるで分らず、まずは、搬入には現地に行かなくてはならない。また、代金については、半金前払いでも良いとのことであった。けれども、まるでわからない話なので、WCES後、VTLの会社に寄るから、そのとき返事するとのことで話を収めた。
この話は眉唾ものかも知れないと私の人脈で探ってみたところ、何と、モニタースピーカーはレイ・オーディオの大型モニターを採用するとのことであった。
この話は本当であって、後日、MJ誌には、レイ・オーディオの木下さんは現地に向かい、現地で納入に立ち会い、パフォーマンスを確認して帰国した状況を記事として掲載されていた。
VTLの会社所在地はロサンゼルス郊外のCHINA(中国人が多く住んでいた地域)と言うので、WCES終了後、車で、私を含めた日本人3名でVTLに向かった。ちょうど、ラスベガスからの帰り道でもあった。
VTLの会社規模は20名程度の従業員で、真空管アンプを主に作っていた。トランス類は自家製で、併せカバータイプでワイルドな外観であった。デザインはダサいという定評を払拭しようと新しいデザインのアンプを開発中とのことであった。
アンプはすべてプリント基板を採用していた。パワーアンプ増幅回路はコンデンサー結合のリーク・ムラードタイプで、多極管を採用していた。DAVID MNLEYが出迎えてくれた。例のスタジオ用パワーアンプのお話はビジネスが遠隔地で実績も乏しいので断った。
特に問題はなかった。
MANLEYさんは若い女性を連れていたので、“お嬢さん?”と聞いたら、“ノー、マイ ワイフ!”と言われてしまった。聞いたところでは、VTLの従業員であった彼女はDAVIDの後妻になったとのことであった。彼女はプリント基板や真空管に詳しく、実質、VTLの社内を切り盛りしている感じであった。
私は、プロ用アンプの売り込みはうまくいかなかったが、代わりに、VTLの輸入代理店業務をやってみるかという気持ちになった。
そんなわけで、サンプルとして、EL34ppプリメインアンプ、100Wハイパワーアンプ、ラインアンプの3台を、その場で注文した。
また、“このスピーカーを聴いてみろ!”と言われて、TANNOYの10インチ同軸ユニットを採用したモニターSP(ML−10)を聴かされた。TANNOYは、いぶし銀サウンドと言われるが、そのようなサウンドでなく、ガッツのあるモニターサウンドであった。
内容を聞いてみると、マスタリングエンジニアとして有名なダグラス サックスと共同で開発したモニタースピーカーであった。このサウンドを気に入った私は、自分用に1台、会社用に1台、計2台(後日、1台追加注文したので併せて3台)を注文した。
帰国してしばらくして、VTLの輸入代理店になる話は、BSRジャパンのOBのYさんが独立して輸入業務を担当することになって、この話もだめになった。
後日談だが、その後、VTLは息子が継承して、DAVID MANLEYはMANLEY LABを設立し、別の会社となった。私は、MANLEY LABOにはマスターズを設立した以後も真空管の輸入先としてお世話になった。
両方の会社は現在でも継続しているが、MANLEY LABOは、MANLEYさんが高齢のため、後妻のエバンナさんが会社を運営していると言う。
プロ用アンプの結末
WCESから帰国して、状況を伝えた。アメリカのI・Fさんの意見も、アメリカはこれから不景気になるから、ビジネスは難しいということだった。同行した佐々木硝子のスピーカーも売れず、アメリカで不良在庫となり、処分したとのことであった。ほどなく、佐々木硝子は経営状況が苦しくなって破綻した。
(株)CTSにおけるプロ用アンプは、スタジオ用ではなくSR(PA)用アンプとして方向転換することも探ってみたが、SR用アンプは価格が安いことが必要条件であって、アメリカ現地のQSCなどのアンプは安く、また、アメリカに輸出していたSR用アンプは安価で、このジャンルはハイパワーをいかに安く作れるかがキーポイントになっていた。
だから、入力信号レベルで動作点を変動させて、アンプの効率をアップさせる小型・ハイパワー・ロープライスが当たり前になっていた。
このような状況で、このプロジェクトは失敗に終わった。ほとんどの責任は私にあった。
残ったサンプルは、タモン(現BIK):スピーカーブランドの越谷事業所の、スピーカーのハイパワー耐久試験アンプとなって今も働いている。
プロ用アンプのプロジェクトは、サンスイに続き、2度目の失敗であった。
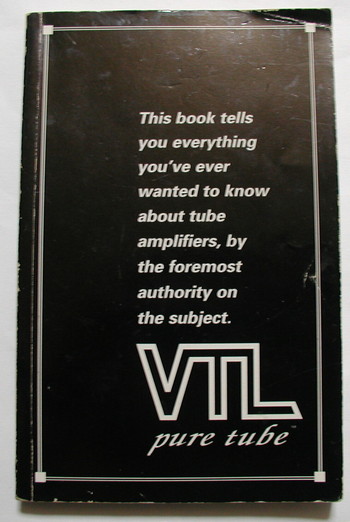
【David Manleyが書いた書籍】
つたない文章をお読みくださってありがとうございます。まだ、まだ、続きます!
2013年 9月 5日掲載