イシノラボ/マスターズ店長の連載
第1弾 日本オーディオ史
第20回 Dシリーズの発売とAU−X1の開発
D(ダイアモンド差動)シリーズの発売
1978年の10月下旬にAU−D907は発売になった。この頃のオーディオメーカーは、コンポも大量に売れたので、全国主要都市で新製品発表会を開いた。会場は、一流ホテルであった。東京、大阪、名古屋、福岡、仙台、札幌と、今では全く考えられない、”信じられないこと!”であった。
発表会会場には、評論家の方々、オーディオ雑誌編集の方、販売店の方、それぞれの受け持ちの社員が持ち構えて、説明・接待するのであった。わたしも全国6箇所を出張した。勿論、他社もそうしていた。それ程良く売れたが、全体的にみると、採算は取れていなかったと思う。山水はJBLという利益の取れる商品があったので、まだ良いほうであった。この頃のオーディオ産業は利益なき繁栄産業であったのだ。全国のオーディオ店は2000店くらいあったから、初ロット生産分はお客様が仮に買わなくとも、1000台くらいはあっという間に店頭展示用に売れてしまう。
ともかく、家電産業は現在でもデジタル家電の値下げ競争が続いているが、これはメーカーと販売双方の、「安く売って売上を上げることだけ考え、利益を考えていない営業体質」が抜けきらないようだ。でも、当時は輸出が好調であったから、会社全体での成長は大きかった。
AU−D907の初ロットの出来栄えは、音質的には量産試作機に及ばなかった。わたしは少し心配になった。わずかに乾いた感じの音質になっていたのだ。勢いというのは恐ろしいもので、オーディオ誌の評価は絶賛に近い内容であったせいか、売れ行きはスムーズで、すぐ、第二ロットの生産に入っていった。私を含めたスタッフは工場に行き、改善に努めた結果、量産試作機に遜色ない出来栄えとなった。これまで、良い意味で評論家SOさんに言われた、「AU−607でのゴム質」という感触はまったく払拭して、パワフル、スムーズ、奥行き感の表現も文句なかった。また、JBLとの相性が良く、クラシックよりもジャズ系音源のほうが気持ち良く聴けた。
MCカートリッジとの相性はそこそこで、やや不満が残った。多くのユーザーはMM型で聴いているようだった。次の機種では、MCカートリッジ対応をどうすべきかの課題が残っていた。また、出来れば、クラシック音源ももう少ししっとり聴かせたかった。
当時のオーディオフェアは、晴海の催事会場のすべてを借り切ったような状態で、大盛況であった。各ブースを彩るショーモデルの女性にオーディオ系男性が群がって、写真撮影をしていた。勿論、山水のブースはAU−D907をメインテーマに掲げて、大いに気勢が上がった。これらのことは他社も同じように売れたであろうし、当時はそれだけオーディオはホットだったということである。
また、後続の下位機種のAU−D607、AU−D707も発売でき、この年1978年にダイアモンド差動回路を採用したプリメインアンプが3機種そろい踏みしたわけであった。こうして、1978年は暮れた。
1078年暮れから1979年の春に発売になったオーディオ記事を読み返してみると、実にこの3機種、とりわけ、AU−D907が紹介例が多かった。ちなみに当時、評判の良かった高級プリメインはヤマハCA−2000であった。この2機種で高級プリメインアンプを2分した感じであった。
AU−X1の構想
AU−607/707に関わっていた頃から、山水はいずれセパレートアンプを発売して、世に問いたいと思っていた。それより前にCA−3000、BA−3000、BA−5000という高級セパレートシリーズがあったが、マッキントッシュに範を採ったオートフォーマー付きのBA−5000はそのタフでしっかりしたサウンドは評判良かったが、その重量から多くは売れなかった。
ダイアモンド差動回路はプリメイン3機種で何とか実績が出来たら、次はセパレートアンプではないかと考えていたが、やはり、そこまでの段階にはまだまだ実力、ノウハウ、などなどが足りないと思ってしまった。
そこで、これ以上他に無いプリメインアンプを発売しようと考えた。幸い、反対意見はなかった。最初のモデル名はAU−DIということになっていたが、車のアウディと似ているので、AU−X1にしようということになった。
その商品化企画は以下のようなものであった。
- 最高級、ハイパワー、大型プリメインアンプ
- 機能はセパレートアンプとしても使えるように工夫する。
- トーンコントロールは省略して、音質優先にする。
- 具体的仕様:
- 最大出力: 170W+170W(8Ω)
- サイズ: 特に制限しない。
- 重量: 特に制限しない。
- 回路構成:
- パワーアンプ: ダイアモンド差動回路
- フラットアンプ: DCアンプ構成
- フォノイコライザー: ダイアモンド差動回路
- MCヘッドアンプ: FETコンプリメンタリ構成
このような大まかな企画内容であった。このような企画に対して、技術機構設計チームは、「フロントパネルは、どうせやるなら、ダイキャストでやりたい」と言ってきた。現在もアンプのフロントパネルは、パネル断面の押し型を作って、アルミを押し出し、それをパネルの長さに切断して、ボリュームなどの穴あけをして、加工して、そのあと、アルマイト加工(一種のメッキ)でシルバー、シャンペンゴールド、ブラックなどのカラーを付けるのである。ダイキャストはフロントパネル全部の型を作って、いっきょにフロントパネルを作るのであった。カメラのような精密機械には適しているが、オーディオアンプには適しているかどうか、何よりもその金型費が、それだけで軽く¥2000万を超えるといわれた。なぜ、そのような方向になったは今でもわたしはよく分からない。アルミ押し出し金型のたて寸法が制限を超えていたからであろうか?
さすがに、金型費がこれだけ高額になると、経営陣もすぐにはOKはくれなかった。
TU−X1の構想
山水のチューナーは、当時のトリオ(現ケンウッド)と比べて、なかなか評判が取れなかった。事実、プリメインアンプにデザインを合わせたTU−707の売上は、プリメインの20%程度しかなかった。当時までの山水としては、傑作はTU−9900くらいしかなかった。AU−9500とペアになったTU−9500にしても、内部が空いていて運動会が開けると言われる始末であった。
丁度、この頃、山水ではAMステレオ放送方式の研究をしていた。いろいろな方式が提案されたが、結局、アメリカの方式となって、山水方式は敗れた。やはり、業界を動かすとなると、それだけの影響力を持つ会社であるとか、ドルビーさんのように、ユダヤ人的な賢さがないと、方式採用ビジネスは成功しないのである。
そこで、山水はAMステレオ方式の技術を利用して、同期検波方式でAM放送を高品位で受信できる技術を開発した。EIAJで発表したが、それ程の反響はなかった。オーディオジャーナルも特に採り上げてくれなかった。それはそうだろう。当時はFM多局化が叫ばれていた時代で、いまさらAM放送については関心がなかったのであった。
試作機を聴かされると確かに良いサウンドでAM放送が聴ける。しかし、世の中はステレオ時代、高品位のモノラルは商売にならなかった。それでも、何とか商品化したいとの開発部門の熱意に、この方式を搭載したAM/FMチューナーを商品化する方向となった。そこで、前述のAU−X1とペアのかたちで発売することがようやく決まった。しかし、採算が取れる予測は立たなかった。言い訳としては、MKII化をして、ロングライフ商品として、ダイキャスト金型費をせっせと償却するほかなかった。
AU−X1の内容の詰め
やっと、高級・究極・ハイパワープリメインアンプAU−X1の開発許可が下りた。
上記のようなハイパワーなので、170Wパワーに耐えうるヒートシンクが無かった。AU−D907にしても、これまでおこしたヒートシンクを2個組み合わせて実現したものであった。機構設計チームは究極を狙っていたので、ヒートシンクも専用のヒートシンク金型を起こそうと譲らなかった。どうして、当時、ここまで、思い切ってしまったのかは、今でも良く分からない。他社を見てもここまでやるようなプリメインプは無かったように思う。当然、事前に需要予測はおこなうが、せいぜい3000台が良いところであった。しかし、なぜかこの機種は金型をかけて、開発していまった。責任があるとすれば、当時私が異常に執念を燃やしていたのかも知れない。
ダイキャスト金型による大型ヒートシンクは今でも手元にあるが、巨大・立派である。トランジスタはAU−D907と同じように、非磁性体構造のLAPTを3ペアパラレル接続で170Wを出すことにした。当然4Ω負荷を保証するので、4Ω負荷では300W近くパワーが出ることになる。
電源トランスは大容量で、当然EI型トランスでは筐体に収容できず、トロイダルトランスを採用するしかなかった。トロイダルトランスの欠点はハイパワーを出しているとき、いわゆる動的状態では、比較的リーケージフラックスが多くなることであった。このことはトランスメーカーが解析してくれた。従って、そのような場合にプリドライブ段、フラットアンプ、フォノイコライザー段への電源供給は別のトランスでおこなったほうが音質的に有利になる。そこで、AU−D907と同様、この電源供給には70VAのEIトランスを搭載することにした。当然、電源部はすごく巨大で重くなった。
また、音質に関係するブロックケミコンは重要であった。メーカーの選択は資材政策もあって、エルナーを採用することになった。エルナー技術陣も大いに張り切って開発に協力してくれた。(今でも当時の技術の方とはお付き合いがある。) コンデンサはパラレル接続したほうが、内部抵抗が低くなり、音質上優位になるので、パラレル接続でいこうということになった。L側に4本、R側に4本と巨大なヒートシンクの直近に8本のブロックケミコンが並ぶことになった。
AU−X1のマスターボリュームをどうしようかと思っていたとき、松下部品事業部から、CP(コンダクティブ・プラスティク)抵抗体のボリュームの紹介があった。CPボリュームといえば、プロ用フェーダーに採用されていた高級品であった。さすが、松下と思った。すぐ、採用することにした。コストも内容からしては高価ではなかった。 しかし、後日談として、量産時に回転トルクにばらつきが大きく、クレームを伝えたら、すぐ、供給停止、生産も停止したようであった。おそらく、2ロットくらいで、アルプスに変わったのではないかと思う。
さて、パワーアンプ、プリアンプとして使えることをメインコンセプトとしたいので、モード切替名称はどうすべきかを考えた。「POWER AMP OPERATION」という言葉がふっと浮かんだので、これを提案したところ、採用された。また、バランスボリュームはパワーアンプのL/Rのゲインボリュームで兼用することとして、マニアックになった。このあたりはその後、NECのA−10で採用されたし、最近ではウエストリバーアンプ「WRI−βZERO」でも採用している。
プリアンプ部はフラットアンプもDCアンプであったが、ここの音質にこだわったあまり、あとで問題を起こすことになったことは後述する。MCヘッドアンプはFETを6パラ接続して採用することになったが、ヘッドアンプだけの試作品を聴いて失望した。しかし、これ以上のものは現在出来ないので、やむを得なかった。今後の機種は別のかたちでMCカートリッジに対応しなくてはと強く思った。少なくともFETはMCカートリッジにはぼんやりした音質で合わなかった。
そうこうしているうちに試作品が出来上がった。横幅480mm、パネル高さ180mm、奥行き450mm、重さは28kgと巨大なアンプとなった。アンプとしてはすばらしいものが出来ると思った。けれども、リスニングルームにこれだけ巨大アンプをおける方はそれほど多くないとは感じていた。
ユニークチューナーTU−X1も試作品が出来上がってきた。これも同じシャーシを使っているので巨大であった。ユニークなのはダイヤルがAMとFMと別個に2針あることで、それほど売れ行きは期待出来ないにしてもユニークチューナーになることは確実であった。 また、生録の仲間から、八木アンテナの方を紹介してくれたので、せっかくの高性能AMチューナーであるのだから、AM専用アンテナを開発・商品化することになった。これは短期間で商品化できた。おそらく、ハイファイコンポ業界でのアクセサリーで、AMアンテナは最初で最後であった。
またまた、お読みくださり、大感謝である。また次回をお楽しみに!

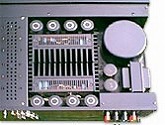
AU−X1 au-607.com様に特別に掲載許可をいただきました。
2006年11月18日掲載
|
第19回 音質検討とその評価について |
第1弾 日本オーディオ史 |
第21回 AU−X1のトラブル |





