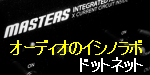オーディオアンプは、スピーカーを動作させて音を出させる機器です。
けれども、設計・製作するうえで、アンプ技術者はどの程度理解しているのでしょうか?
動作原理
フレミングの左手の法則で、磁界の中に電流が流れれば、90度の方向に力が働くことで振動体が動く。このことは電動機(モーター)と同じです。音響振動を電流に替えた機器(オーディオアンプ)で、振動体を動かし、空気を動かし、音にします。
スピーカーの周波数特性は定電圧と定電流ドライブとで異なる
スピーカーの周波数特性は定電圧と定電流ドライブとで異なります。
定電圧ドライブとは、負荷インピーダンスが変化しようと一定電圧を供給することです。具体的には、8Ωと4Ωと変わっても送る電圧は変わらないから、負荷には2倍の電流が流れます。
スピーカーの周波数特性を測定するには、定電圧で出てくる音の大きさを測ろうとする方法が80年以上前、デンマークのB&K社が決めた以来、踏襲されています。
真空管アンプ時代にはB&Kの測定用ドライブアンプは6AR5ppで、多量のNFBが掛かっていました。
半導体アンプは多量(40~50dB程度、多量のNFBが掛かっていますから、定電圧特性に近い性能です)、特に、多数パラレルパワーデバイスを投入し、大変低い内部抵抗で作られているアキュフェーズアンプは定電圧アンプに近いでしょう。そこまで厳密に言わなくとも、アンプのDFが50以上あればそう言っても間違いはないと思います。従って、スピーカーカタログに載っているような周波数特性で聴いていると思われます。
一方、定電流ドライブは負荷インピーダンスが変わろうとも、一定電流を送り続ける方式です。具体的には、負荷より大きな内部インピーダンスアンプでスピーカーをドライブすることが定電流ドライブ方式です。
具体的には、100Ω程度の抵抗を直列に接続してスピーカーをドライブすれば、定電流ドライブと言えましょう。この方法で、スピーカー両端子の電圧を測定すると、いわゆるインピーダンスカーブが分かります。
半導体アンプと真空管アンプのサウンドの違い
半導体アンプと真空管アンプとで、出てくるサウンドにどのような違いがでてくるでしょうか?
半導体アンプは定電圧アンプと考えると、スピーカーシステムのインピーダンスが変わろうとも、スピーカー端子にかかる電圧は変わらないので、スピーカー設計者の自由度は広がります。
特に、ネットワーク設計において、回路教科書に書いてあるような定インピーダンス型のネットワークにすると、ほとんどのスピーカーはクロスオーバー帯域で周波数特性がアップして、うるさい音になってしまいます。
これは、ある程度、理論値よりも小型にスピーカーシステムはつくらないと、ユーザーは置き場所に困り、買ってくれないことになります。
その解決法がクロスオーバー帯域のネットワーク定数をずらすことです。
具体的に、500Hzでクロスさせるネットワークは、計算上ではWFは300Hzくらいに、TWは1kHzくらいに、ずらすことがおこなわれます。
当然、インピーダンスは規定インピーダンスよりアップします。
アップした帯域では、各ユニットへの電圧供給が低下するので、周波数特性の上昇は修正されます。
このようにして、スピーカーエンジニアは周波数特性を測定したり、ヒアリングをおこなって、ネットワーク定数を決めます。
一方、そのようなインピーダンス特性になったスピーカーシステムを定電流アンプにドライブするとどうなるでしょう。
定電流アンプに代表されるものとして、例えばEL34シングルアンプで駆動したら、クロスオーバー付近の帯域にも定電流が流れます。従って、アンプ負荷が軽くなるので、スピーカーにかかる電圧はアップし、その帯域の周波数特性は少し持ち上がります。このあたりが、真空管アンプで聴けばサウンドが暖かく、ゆったりすると言われる所以です。
もちろん、真空管アンプでも多量(20dB以上)のNFBを掛けることが可能なユニットカップルアンプのマッキントッシュMC275とか、OTLアンプは定電圧/定電流アンプの中間的な特性であり、そのあたりがまた、異なるサウンドとなって楽しむことができると言えましょう。
スピーカーの効率とアンプ出力
スピーカーの効率は非常に低く、正確なことは記述できませんが、効率90dBのスピーカーでも効率は1%以下と思われます。
99%以上、ボイスコイルの抵抗で熱になって消費されてしまいます。
このような低効率の原因は、空気を動かして音にすることは大変なのです。
専門的には、振動体のインピーダンスと空気のインピーダンスとのミスマッチングによるものです。振動板の面積が大きくなれば、振動系質量を軽くして、磁気回路の磁束密度が大きくなれば改善されます。最も効果的なのは、振動体にホーンを付けて、インピーダンスマッチングを図ることですが、ホーンを通り抜けるときに反射が発生するので、特有の音色が付くことが少なくありません。
それでも、1W入力を入れて、1m離れた地点で90dBもの大きな音が出てくれれば、それほどのエネルギー消費にはならないと思います。
けれども、近年のスピーカーシステムの効率は、カタログに示す値で88dBと記載されていても、実際に測定してみると(ステレオサウンド168号で掲載されている)カタログ値よりも3dB~4dB低いのです。これは、メーカー側が何とか良い数値を示そうとある程度の良い数値を当てはめているのです。
このことを詮索しても、ほぼすべてのブランドがそうしているので、“みんなでやってしまえば、良いだろう!”という心理があるではないかと思います。
さらに、インピーダンス8Ωスピーカーの実測インピーダンスは、中低域においては4~6Ωと低くなっています。こうなると、1W/8Ωの電圧をスピーカーにアンプパワーを入力させれば、4Ωならば2倍のパワーが入っていることになり、2Wの入力が入っていることになります。
それほど、本当のことを表示しないのは、スピーカー効率が低いことのうしろめたさがあるのかも知れません。
その気持ちは、かつてのWEのスピーカーの効率は20%程度もあったからです。
ホーンドライバーの場合、高効率になるので、このようないわゆる“うそ表示”はないと思われます。
ちなみに、私がスピーカー設計をしていた1960年代では、割と正直な効率表示をカタログに載せていました。
結局、近年のスピーカーシステムは小型化を迫られ、そうかといって周波数特性を狭めることができず、振動面積の小さいユニットを小さいキャビネットに付けることによる低域不足を、振動系を重くして対処しているので、効率は低下しています。
幸い、アンプ出力の増大は可能だったので、ある程度の誇大表示はユーザーにとっても許されたのでしょう。
象徴的なことが、1980年代頃までのスタジオモニターは38cmウーファーを採用した大型システムでした。今はNS-10Mクラスの小型スピーカーが主力です。
少し話がそれましたが、具体的に記してみましょう。
- 多くのスピーカーシステムの実測平均効率は87dB(公称8Ω表示)くらいです。1m離れた地点で90dBの音を聴こうとすれば、アンプは3dB分、多くパワーをスピーカーに注入しなければなりません。
そうなると、アンプ出力は2倍の2W必要になります。
2m離れて90dBの音を聴こうすると、さらに4倍の8Wになります。
90dBの音は相当うるさい音です(無響室内で聴くと部屋の反射がないので、何とか我慢できる音です)。
ところが、普通の部屋で聴くと反射が多くなるので、我慢できないくらいのうるさい音になります。ff時の再生のためには、アンプ出力は8Wもあれば良いのです。 - 上記の話は、現実をはるかに超えたうるさい音の世界です。
皆さん、ff時、80dB程度が近所迷惑にならない限界と思います。
そうなると、10dB下がるとアンプ出力は1/10の0.8Wあれば充分です。
そして、皆さんの聴いている平均音圧レベルはさらに10dB下がった音量と思われます。アンプは0.08W(80mW)になります。そのときのアンプ出力電圧に換算すると、0.8V(8Ωスピーカー)と小さい値になることが分かります。 - 遮音をしっかり施した大きなリスニングルーム(14畳とか)を持てる方なら、4mくらい離れて聴くと、2mの場合の4倍の32Wになります。
せいぜい、30Wの出力を有するアンプがあれば、99%の方は満足できるでしょう。 - けれども、オーディオ界には、100Wとか200Wとかのハイパワーがそれなりに売れています。これは3000ccの車で時速40kmで走行するような感じを楽しんでいるようなものです。
- 一方、50kgのヘビーウエイトの純Aクラスアンプも同時に売れているということは興味深い現象です。細かい話ですが、純Aクラス、50W/8Ωのアンプもスピーカーのインピーダンスが先述のように下がってしまうと、ABクラス動作になってしまいますし、アイドリング時を含めた消費電力は膨大で、夏季には使用を避けたいものです。
- マスターズのAクラス動作アンプは、マッチングトランスによってアンプは80Ω以上の負荷で動作するので、消費電力は通常のアンプより少ないくらいで、Aクラス領域で動作しています。
このようなアンプは大げさに言えば、マスターズにあるだけです。 - マッキントッシュの半導体トランス付きアンプは、逆にABクラスで動作するようにハイパワーを維持する目的で採用されていると想像します。