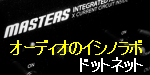バランス伝送
私がバランス伝送に他のエンジニアより慣れていたのは、多次元音場システムの開発時、プロ現場に慣れ親しんだからともいえます。
まず、バランス伝送にしないと、外来ノイズを引きやすいので、プロ現場でアンバラで取り扱うことはまずありません。
録音現場、マスタリング、SR(PA)、放送局、ホール拡声などです。
どうしても、伝送路が増えるので面倒ですが、オーディオ信号の品質維持に欠かせないものです。
一方、家庭用途のオーディオ機器は伝送距離も短く、電磁ノイズ、電磁波ノイズで悩まされることはまずありません。
特に、バランス伝送にこだわる必要はありませんが、グランドに基づくノイズの存在があります。
かつて、ケンウッドで委託設計したとき、彼等はグランドを下水と呼んでいました。私は、下水と上水とが一緒くたになったアンバランスアンプに違和感を覚えました。
むしろ、グランドと関係なく、フロート状態で伝送したほうが良い!との感触がありました。
一方、家庭用オーディオ機器のためのソフト、例えば、カッティングマシンはそれほど詳しくありませんが、おそらくカッターはバランス信号で動作させるか、または、ドライブアンプがアンバランス方式なら、バランス→アンバランス変換してからカッティングしているかも知れません。
CDはバランス→アンバランス変換してプレスされるか、それともバランス信号でプレスされるかになるのでしょう。
要はすべてのプログラムソースはバランス伝送によって制作されるのです。
また、気になるのは、DC→ADに変換されるとき、DACIC内部回路で、自然とバランス信号(コールド)が生じるのです。
従って、CDプレーヤーはわざわざ、アンバランス信号に変換して出力されているのです。
そのため、DAC単体で販売されているものには特に費用を掛けなくとも、バランス出力が出せるのです。
アンプのこと
オーディオアンプは1970年代、半導体アンプが主体となってから、100%入力差動構成になっています。
差動構成とは、入力に+(ホット)、-(コールド)があって、グランドに関係なく入力間の差分で動作するのです。
そこで、便宜的方法とした、差動入力の片方をグランドに接続して、アンバランス増幅に仕立てたのです。
こうすることによって、NFBもホット~コールド間に施すことで成立します。
要は、半導体アンプは電圧増幅段の半分を利用していないのです。
この方式は“ハーフブリッジ・シングルエンデッド・プッシュプル”と呼びます。車で言えば、前輪ないし、後輪ドライブ車に例えられるでしょう。
従って、NFBの基準点はグランド(下水)なのです。
ちょうど、整流コンデンサからのリップル分がグランドへ流れ込み、混在します。
これらの配線取り扱いを間違えるとハムノイズが出てきます。このあたりがアンプ作りの年期と言えるのでしょう。
現状の半導体アンプは回路の半分しか使っていないし、グランド(下水)の影響をまともに受けているのです。
この現象を少しでも軽減するのがMASTERSのXカレントアンプです。
スピーカーのこと
ここまでが、ある程度常識化されたことですが、意外とみなさん、無頓着なのはスピーカーについてです。
ご承知のように、スピーカーのボイスコイルには極性がありません。
だから、JBLは極性が最近まで逆になっていました。
私はスピーカーの量産設計経験から、わざわざ、片方をグランド側に接続して動作させることには違和感を覚えました。
それよりも、スピーカーのボイスコイルをアンプのHOT、COLD成分で、グランド(下水)の影響を受けないことを考えました。
当時、私は山水電気でアンプ回路開発に従事していたので、この提案は段々と受け入れられ、Xバランスとネーミングされました。命名は故、前園さんです。
MASTERSのZバランスは、この回路をシンプルかつピュアに作り直したものです。
Xバランスは3段増幅、Zバランスは2段増幅
サンスイは終焉まで、約30年間Xバランスを踏襲しました。
Zバランスアンプ回路は2段増幅に改良した結果、位相補償コンデンサは3Pf、1カ所だけで済みます。
SEコンのような高価なマイカコンを使用する必要がありませんし、オープンループ特性も抑えてあるので、NFB量は多くはありません。
仕上がりゲイン10dBのアンプにしても、安定度には全く問題ありませんでした。
この方式を“フルブリッジ・ダブルエンド・ダブルプッシュプル”と呼べるでしょう。
車で言えば、4連駆動車に例えられるでしょう。
悪路、雪道、山道でも、苦労なく楽々走るでしょう。
もちろん、ファイナル段の整流コンデンサはグランドからフロートされています。
従って、当社のCA-999シリーズを採用すれば、DAC~パッシブプリアンプ~パワーアンプ~スピーカーまで、グランド(下水)からフリーとなって、バランス増幅が成立します。
このようなコンセプトに近いアンプは、私がリスペクトしているテクニカルブレーンの黒沢さんのアンプだけです。
また、Xバランス採用の山水アンプの修理は、上記コンセプトの理解が必要です。