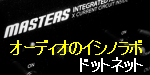2019年が明けました。おめでとうございます。2018年は大変、皆様に応援いただき何とか継続できております。本音では、一日、一日がもう少しゆっくり経過しないかと願いつつ、1年はあっと言う間です。
私は3年日記を書いていますが、2019年で5冊目になります。読み返しても、大した人生ではないと悟りつつの毎日です。
私は基本的なアンプの開発・設計・製作アプローチについていつも考えています。
まとまりませんが、思うところをとりあえず記述してみました。
オーディオ界のオーディオアンプ
オーディオ機器のうち、オーディオアンプ(以下、アンプと書く)は振動~電気変換部分がなく、純エレクトロニクス製品と考えます。
今回は、アナログアンプ、それも半導体アンプをベースとして記述することに致します。
アンプの評価を語るに際して、現在まで、その測定・評価方法は連続信号(トーン・バースト信号にしても)に対する応答であって、その結果が優れていたからと言って、アンプの評価にならないことは常識になっていますが、悪いより、良いほうが良いと言えましょう。
それではパルス波形に対して、FF解析にしてもその結果の評価はマチマチです。
けれども、そのアンプの性格付けにはある程度役に立っています。
日本のオーディオ誌、オーディオクラフト誌においてはメーカー品の電気測定はまったくおこなわれておりません。40年くらい前くらいまでは、おこなわれていたこともありますが、いつの間にか無くなりました。
その根本原因は、オーディオは最終的に“聴いてナンボ!”の世界と言うからなのです。聴き方の好み、背景、環境等の因子での話になりますが、それは仕方のないところでしょう。
それでも、以下、作り手の立場から、述べてみます。
アプローチの方向
A志向:大きくとらえるやり方
例えて言えば、“木を見て、森、いや、森林をみる!”とか、格闘技に例えれば、“フォール勝ち、一本勝ち”というように、大技を優先する考え方とも言えます。
B志向:細部から詰めていくやり方
この方向性を好む方は日本ではかなり多いです。何かを前提で固定して、その短所や問題点を、段階を追って、主として対策を施すのをメインとするやり方と言えます。
“木を見て、枝、葉っぱを見る!”というような、格闘技で言えば、“得点を重ねて、優勢勝ちや、判定勝ちを得るような、こつこつ、重ねていくようなやり方と言い換えられましょうか?
具体的なアプローチ例
A志向:JBLに在籍したバート・ロカンシーは画期的な回路を実現しました。すなわち、差動入力、全段直結、コンプリメンタリー回路です。
この回路はJBLのSE-400やSA-600に採用され、その後の日本のアンプブランドに大きな影響を与えました。
と言うのは、回路の細部を眺めれば、少なからず問題はあったかも知れませんが、ともかく、それまで見たことのない回路だったと言えましょう。
B志向:上記回路に様々に改良を加えて、ひずみ低減競争を繰り広げたのが1970年代後半の日本ブランドのアンプです。そのために、高域特性の良好な半導体を開発したりして、回路細部を検討して、0.003%という低ひずみを各社達成しました。
一方、ヒアリングに徹し、特に部品、とりわけコンデンサーや抵抗を交換して良くなったと認識する方法です。
この動きに日本の部品メーカーは乗ってくれて、利益が出ているうちは協力的でした。
1970年当時、あれだけ力の入った音質部品は2000年にはほとんど無くなってしまいました。
あのブラックゲートケミコンも突然、姿を消してしまいました。
電源ケーブルについても、このような志向によって誕生したのではないでしょうか?
銅の純度を高めたり、銅の結晶を大きくしたりしたケーブルが好評でした。それからずっと、オーディオケーブルはビジネスになりますから、いろいろな細かい方向性によって、ケーブルは百科繚乱と言えましょう。
そもそも、家庭内の電源コンセントにくるまでの電源経路は柱上トランスから、多くは20m以上の長さで配線され、それから、漏電検知器、ブレーカーを経て、屋内配線(Fケーブル)されてきます。
そこから、アンプの電源ケーブル(2mくらい)でサウンドが変化すると言うオーディオは面白いと思います。
A志向的に、専用柱上トランスを用意して、オーディオ専用電源配線とすれば、電源ケーブル問題は、かなり劇的に認識されると思います。
マスターズの考えるアプローチ
私はどちらかと言えば、A志向的です。
具体的なケースで記述してみたいと思います。
プリアンプ:プリアンプはCDプレーヤーの出力が大きいので、アナログレコード時代のような増幅度は必要なく、むしろ、入力信号を減衰させる形でパワーアンプにオーディオ信号を送り込んでいるような状況です。
そうなると、アクティブプリアンプで構成するには、オープンループゲインが余ってしまい、多量のNFBによって、増幅度を抑えることになります。
そうなると、過度のNFBを主原因とするTIMひずみが多くなり、いわゆる過渡ひずみがヒアリング時、耳についてくるようになります。
(注)TIM歪(Transient Intermodulation distortion)とは、フィンランドの物理学者でオーディオ研究家のマッティ・オタラ氏が提唱したもので、THDが低い低歪アンプでも過渡応答が良くないアンプは音が悪い。オタラさんは1977年、サンスイにも来訪されて、この現象を説明しました。
この対策としてはB志向アプローチでは、位相補償回路の工夫によって、負性抵抗部をより少なくすることがおこなわれます。
この対策は、位相マージン改善は75度くらいの確保が限界です。連続信号では、位相がずれてNFB演算しても、高調波ひずみを減らすことはできます。
ところが、音楽のような過渡信号には、NFBにより演算は位相がずれるに従って、混変調状態となって音質上有害になります。
(但し、この現象が生じるのは可聴帯域外付近とかそれ以上の帯域になるので、気が付かない場合も多いです。)
その意味では、アクティブプリアンプの設計は難しいと思います。残るアプローチとしては、コンデンサー、抵抗、配線ケーブルを交換してみる作業になるのでしょう。
おそらく、この作業によって、音調は変化しますから、聴きやすいプリアンプへと導くことはけっこうおこなわれていました。
私がサンスイ在籍時、C-2302の開発に携わったときは、上記対策に加えて、増幅回路スルーレートを大きくすることにより改善されたと思っています。
マスターズが考えるアクティブプリアンプは、以下のようなアプローチでおこなっています。
その回路的な方向性としては、まず、NFB量をできるだけ少なくし、増幅度が多くなってしまった分は固定抵抗により減衰させております。
アンプのS/N比はオープンループ特性によって決まってきますので、S/N比はNFB量や減衰量では変化はありません。
そしてできるだけスルーレートを大きくして、TIMひずみの少ないサウンドになったと思います。
最近では、カスタム注文によって製作した300Bバランスプリアンプ(【図1】参照)は、のびのびとしたサウンドで、まったくTIMひずみ現象はなく、気持ちよいサウンドです。
そのうえで、片ch4連ボリューム方式により、音量は-140dBまで絞れ、実使用上、優れた残留ノイズの少ないプリアンプとなりました。
さらなる方向としてはアクティブアンプではなく、パッシブプリアンプへの方向に踏み切りました。
パッシブプリアンプのタイプとしては、ボリューム(フェーダー)方式と単巻トランス方式があります。ボリューム方式はアクティブプリアンプのようなTIMひずみの発生はありません。
けれども、ボリューム方式はボリュームを通すことによって、オーディオ信号のパワーアンプへの出力インピーダンスが高くなりますし、ボリューム位置によって、出力インピーダンスが変動するので、残留ノイズが変動することもあります。どうしてもと言う場合は、実用的な値としては10kΩインピーダンスボリュームがお勧めです。
トランス式パッシブプリアンプも同様、TIMひずみはまったく発生しません、さらに巻線抵抗のみが出力インピーダンスに関係するので、エネルギー消費がなく、出力インピーダンスはせいぜい100~250Ωであり、パワーアンプをパワフルにドライブできます。
トランスと言うと、ひずみが問題ではないかと心配される方がおられます。磁性体は微視的に研究すると、磁界により忠実に磁区が動けば、ひずみが発生しません。
目的を達成するには、ひずみのないコア材を採用することです。
パーマロイコアはMCトランスや通信用トランスに採用されているように、立ち上がり特性(μ)に優れ、ひずみがなく、その素晴らしさは定評があります。
入力する発振器のひずみとパッシブプリアンプの出力とを比較してみて、少し、驚きました。
両者はまったく同じなのです。すなわち、パッシブプリアンプでは歪まず、ノイズも発生しないことです。
音楽のような信号を通して、まったく信号変化はないと推測できます。
実際、ヒアリングしてみて、まったく有害な現象がありません。但し、コア材に最適な巻線設計をおこなうことが必要です。
多くのアンプ設計者は残念ながら、トランスや磁性体に対する知識がイマイチです。
私はたまたま、トランスのタムラ製作所、サンスイ電気に在籍し、いろいろと学び、経験したから実現できたと思っています。
さて、近年、新素材として、ファインメットが登場してきました。
ファインメット情報が広まったのは、かつて、あのWE300Bについての素晴らしさを見つけた新(あたらし)さんの力によることが大きいと思います。
ファインメット材は日立金属開発によるコア材です。その内容はアモルファス結晶コアに巧みなアニール処理を加えたものと言えます。
そして、コア材は0.1mm程度の薄板加工をされているので、渦電流損失も少なく、超高域特性も優れています。パーマロイコアと同等以上の特性を示します。
測定ではまったく検出できませんが、パーマロイとファインメットとのサウンドの違いは、注意深いヒアリングによれば、ある程度指摘できます。
強いて言えば、前者はわずかに寒色系、後者はわずかに暖色系のサウンドと言えそうです。
電源に対する考え方
アンプの電源は重要です。なぜなら、アンプ出力は入力信号がコントロール信号となって、電源供給電力を切り分けた成分であるからです。
このあたりはトランスと基本的に異なることです。従って、電源がアンプ出力も根源ですから、電源が良質でないと良いアンプにはならないからです。
電源トランス電源
電源トランスによって、適性電圧変換して、アンプにDC(直流)を供給します。
具体的には、電源トランスの容量、タイプ(EIとかトロイダルとかカットコアとか)、整流コンデンサー(タイプ、静電容量、使用構成/個数とか)、整流方式(整流管とか、ダイオード(シリコンとか、ファーストリカバリーとか、ショットキー)といろいろあります。それぞれの特長があり、いちがいにどうこうとは断言できません。ケースバイケース、ノウハウがあります。
トランス電源方式の問題点は、整流コンデンサーのマイナスとアンプ(ハーフ・ブリッジSEPP回路)の基準点(マイナス)とが混在して、再生サウンドが濁ってしまう現象です。
多量のNFBによって、電気的性能ではわからない現象です。ヒアリングにおいても、この部分について検討しなければ気が付かない部分です。
実は私も気が付きませんでした。この現象は後年、電流プルーブという測定冶具(高価)を入手して、オシロスコープで眺めることができて、改めて認識できたのです。
この現象を防ぐには、アース(グランド)に関係なく、動作するバランス増幅アンプとするのが有効です。まさに、Zバランス増幅回路はそれにあたります。
そうでないハーフブリッジアンプでは、MASTERSアンプ(AU-900Xシリーズ)ではXカレント電源回路で改善を図っています。
スイッチング電源
近年、家電、携帯等の電源は、大多数スイッチング電源になっています。
スイッチング電源の原理はいったん、商用電源(50Hz/60Hz、100V)をダイオード整流し、整流したDC電圧で高周波発振させて、必要電源を作り出します。
電源トランスを用いないので(発振トランスは必要)、小型/軽量電源ができます。こうできるようになったのは、高周波特性の良好なMOSFETの出現によります。
この電源のオーディオ的問題点は、高周波発振による漏洩成分(スプリアス)のアンプへの飛びつき混入です。
従って、さすがに、スイッチング電源によるMCヘッドヘッドアンプはありません。
電磁波ノイズの影響:電源を通じての電磁波ノイズのアンプへの悪影響はこれだけ携帯やスマホが普及した状況下では深刻です。
電源フィルター、電源ケーブルへの電磁波遮蔽材などがいろいろ販売されています。
装着採用しても、その効果は完璧ではなく、ある意味、気休め的かも知れません。
私はCE安全規格での仕事で、電磁波ノイズがアンプ内部入り込む測定と対策をずいぶんと委託業務としてやりました。
その経験から言うと、電磁波ノイズ成分は数十Mz~2ギガと広くあり、その電磁波ノイズの影響を防ぐのは容易ではありません。
バッテリー電源
それでは、一番、純粋な汚れのない電源とは何でしょう。
私は、電源電圧の制限がありますがバッテリー電源と思います。特に、瞬間電源供給能力のある鉛バッテリーが良いと考えています(ちなみに車始動時に流れる100Aにも充分対応します)。
将来性のあるものとして、化学周期律表からも理解できるように、リチウムは有望です。けれども、安全性が心配無くなれば有望です。
マスターズアンプにおいて、AC電源/バッテリー電源切替アンプがあります。スイッチで切り替えて聴くと、一聴して感知できます。
但し、鉛バッテリーは12Vですので、±12V電源ですと、取り出せるパワーに限界があります。
けれども、ハーフブリッジで8W、フルブリッジでは18W出せるので、ほとんどのリスニングではパワー不足は感じません(あとは充電の手間をどの程度面倒と考えるかです)。
最も有効なバッテリー電源の活かし方は、フォノイコライザーです。マスターズでは近々、バッテリー電源モデルを製品化するつもりです。
リレーの存在
近年の半導体アンプは、アンプ出力にリレーを設置して、リレーを介してスピーカーと接続されるようになっています。どうして、リレーは必要なのでしょうか?
それは、近年の半導体アンプは電源ON/OFF時、ショック音を発生させるからです。振り返って、例えば、JBL SA-600にはリレーは付いていません。
リレーが無くとも、ユーザーから、問題ありとのクレームは無かったと聞いています。
SA-600以後のアンプはコンプレーメンタリー回路ですが、初段差動回路に定電流回路を設置したアンプは、電源ON/OFF時、アンプ電源の±成分が同時に立ち上がることがなく、安定するまでの短時間、アンプ出力からDCが出てしまうのです。
リレーはご存知のように、1mm平方以下の点接点で接続されています。従って、オーディオ信号接続の点では問題ありの部分です。
この接触が悪化すると見事な2次高調波が発生することでも不十分な存在です。言わば必要悪と言えます。
そのせいかどうかは分かりませんが、アキュフェーズアンプはリレーを削除して、超低抵抗のMOSFETを採用しています。
リレーを削除するには、アンプ電源が電源on/OFF時、±電圧が均一に立ち上がり、立ち下がれば、スピーカーからショックノイズが出ることはありません。
MASTERSのアンプは、上記条件をアンプ回路において実現して、リレーを削除することに成功しました。
もちろん、スピーカーへのプロテクションについては充分な対策を講じています。
以上ざっと、記述してみました。たかがオーディオアンプでもいろいろ興味深いです。
A志向的発想のDクラスアンプは、その後のB志向的改善により、Dクラスアンプ内のスイッチングノイズはかなり抑制されてきました。
今後、小型・軽量・高効率というポイントからは有望と思います。
【図1】カスタム注文によって製作した300Bバランスプリアンプ