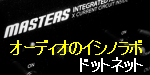特別ご提供品プリアンプ“MASTERS CA-888BL/PHcustom”をエージングを兼ねていろいろ聴いてみました。
特別ご提供品のMASTERS CA-888BL/PHcustomは1台限りで作ったので、やってみたいことを搭載した意欲的なプリアンプです。
そのユニークなワイドユース
- API2520フォノイコライザー回路を搭載しました。APIでは2520の出力を自社製(API)のライントランスでバランス出力することを想定しています。このトランスは山水在籍時、アメリカ出張の際、現地で購入したもので、それから長期間、私の机に中で眠ったままになっていました。ずっと、いつか使ってみようと思っていたバランスライントランスです。このトランスはけっこう大きく、APIコンソールにフォノイコライザーとライントランス含めた基板ユニットになっていました。今回は、付属回路を削除して、フォノイコライザーとライントランスでフォノスター時をまとめました。ですから、フォノバランス出力だけを使うことが出来るようにフォノEQ出力スイッチを設け、ON/OFFできるようにしました。このバランス出力をバランス増幅プリアンプないし、ボリウム付きバランス増幅パワーアンプに接続すれば、バランス増幅アンプでプロ用仕様でAPIユニットのパフォーマンスを楽しめます。
- MCカートリッジ対応はタムラ製MCトランスを内蔵しています。昇圧比は20倍とオルトフォンタイプには少し昇圧比が足りないですが、APIフォノステージのゲインが充分あるので、使えます。また、デノンdl103タイプ、オーディオテクニカの12Ωインピーダンスカートリッジも充分使えます。。
- もっとも、1項のようなことをしなくとも、このプリアンプはバランス増幅ラインアンプを内蔵しているので、スムーズな信号の流れで、バランス伝送・バランス増幅サウンドが楽しめます。
ヒアリング感はどうか?
- CDが登場して35年、そのサウンドの限界は皆さん、感じていると思います。けれども、CDの良さは取扱が簡単、長時間楽しむことができる特長があります。SACDになればそれなりにサウンドは改善されますが、やはり、何か違和感あるサウンドなのはアナログレコード、テープを聴いてしまうと、わかってしまいます。今更、アナログレコードに戻ることはできませんが、手持ちのレコード在庫で充分楽しむこと、レコードの表、裏をひっくり返す面倒を我慢すれば、そのスムーズなサウンドが、やはりこれが本当のサウンドではないかと感じてしまいます。
- 幸い、私のようなレジェンドオーディオ人間は、ある程度の数のカートリッジをいろいろ持っているので、交換して楽しむこともできます。
ヒアリング時の接続はフォノイコライザーのバランス出力をZBバランス増幅パワーアンプに接続しています。
MMカートリッジで聴く(カートリッジ:ピッァリングMP/AC)
このカートリッジは当時、安価(当時¥6,300)で、出力が高く(6mV)、針圧が4g-6gと高く、どちらかと言えばDJ用とされたものですが、あえて、入手してみてその素直なサウンドに気に入っています。どのレコードを掛けても、そのサウンドバランスは中庸で聴き疲れすることがありません。このプリアンプで聴くと、さらに、さわやかで、分解能良好のサウンドが聴けます。シンフォニーのような大規模な音源では、更に気持ち良いサウンドが聴けます。混濁感など、皆無です。当方で販売していた“フィメールボーカル”の本来のアナログレコードでは、さらに密度濃いサウンドが聴けてしまいます。
MCカートリッジで聴く(カートリッジ:オルトフォンMC ROMAN)
このオルトフォンカートリッジはSPUよりもさわやかで切れ味が良いカートリッジです。すぐ、フィメールボーカルアナログレコードで聴いてみました。
まずはガッツな行方サウンドが奥村チヨ、渚ゆう子が聴き取れます。この感じはボーカルがそう聴こえるのではなく、カラオケ(バックオケ)のサウンド処理が素晴らしく躍動感にかられます。このあたりはCD版“フィメールボーカル”はアナログレコードにかなわない感じです。
我田引水かもしれませんが、APIのスタジオサウンドの味わいがこのレコードに合致したのかも知れません。このプリアンプではMCカートリッジで聴く限りクラシックよりもポップス、ジャズのほうがぴったりすると感じております。
そう言いつつ、クラシックのシンフォニーではワルター指揮のコロムビア交響楽団(レコーディング用に編成したオケでストリングスが2プルト:4人編成で非常に少ない)でベートーベンの“田園”を聴くことにします。この録音はともすればハイ上がりバランスになりがちです。けれども、出てきたサウンドは編成が少ないだけに各部の動きがこの接続では聴き取れ、美しいカルフォニアサウンド(カラッとした切れ味の良い)を味わいました。このパフォーマンスはこのプリアンプのおかげが大分あるように感じました。久しぶりにこのようなサウンドを楽しみました。