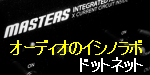2013年ももう3月です。例年のように、年末・年始から、あたふたとアンプ製作に励んでおりました。皆様、いかがお過ごしですか?久しぶりに書きました。
学生時代、電力工学の教授が講義の冒頭、“君たち、アンプとトランスはどう違うか?言ってみなさい!”と質問されました。私を含めて、しどろもどろのことしか言えませんでした。
教授は、“トランスは電磁誘導現象で、エネルギーの電圧・電流を変えて、負荷に伝達する。一方、アンプは入力された信号で、電源エネルギーを比例関係で、相似な状態で負荷に加えることである。お互いは似ているようだが、その原理はまったく異なる。”と言われた。
確かにそのとおりです。けれども、ともすれば、アンプに携わるエンジニアは、アンプ回路がエネルギーを負荷に主体的に伝えると誤解してしまうことが少なくない。要は、アンプは電源をコントロールする装置なのです。
オーディオ科学はまだまだ未知の分野が多く、感性・官能・嗜好等に頼ることが多いのは仕方ありませんが、オーディオアンプにおいて、原理から見れば、一番支配的なのは電源部ということができるでしょう。ところが、100V商用電源の品位は、昨今、スイッチング電源、インバータ等による波形ひずみ(クリップによる)と、電波機器がものすごく多くなったので、電磁波ノイズ混入がひどくなってきています。その対策グッズが、いろいろオーディオアクセサリーとしてオーディオ界をにぎわしています。それですべてが問題解決にはなっていないのが現実と感じております。
オーディオアンプは、まず、電源にどの程度の性能を持たせるか?が重要で、次にコントロール部となるオーディオ増幅回路となるでしょう。
電源は、クリーンでインピーダンスが低く、電源変動が少ないのが理想とされます。その意味からすれば、良質なバッテリーが、アンプとして一番優れることは納得いくと思います。けれども、電源電圧が低いこと、充電の手数などの短所があり、これらを勘案すると、12Vのバッテリーを使用すれば、取り出せるパワーは8Ω負荷で、6W~18Wくらいと大きくはありません。けれども、みなさんが聴いている音圧レベルは88dB程度の効率のSPで、フォルテシモ(ff)のときでも90dB程度で、平均レベルは10mW程度です。
そこで、110dBの高効率のホーンドライバーでは、1W以下のアンプで、超ローノイズのアンプで聴くのが望ましいことははっきりします。
世の中にあるアンプは、100Wでもハイパワーアンプと言える状態ではないですが、このようになってしまったのは、パワーアップすれば良いサウンドになり、高く売れるというビジネス志向による状況が多かったです。私もサンスイに在籍時は、バージョンアップするときは5Wでも10Wでもパワーアップを繰り返しておりました。(100Wアンプが200Wアンプにアップしても、スピーカからの音圧アップは3dBに過ぎません。まして、110Wにしたところで、0.3dBアップです。)
改めて、オーディオを楽しむ皆様に、アンプのパワーは、ほどほどで充分と申し上げます。
いろいろオーディオアンプの特長を見据えて楽しんで下さい。
オーディオアンプは、音楽・音を、スピーカを通して出して聴いて楽しむものです。
趣味・道楽であるからこそ、いろいろな方式、主義主張があって良いと思っていますが、作り手側はそれなりの見解を持っているべきと思っています。
山水電気在籍時や、いろいろなオーディオブランドの委託設計に際して、上記事項について議論とか検討をしたことが懐かしいですし、現在も尽きることはありません。
まず、NFBについては、オーディオ誌では、NFBを必要悪とか、掛けないことが美徳のように書かれていることも少なくありません。
NFBは、H.Sブラックさんがパテント取得以後、あらゆる分野で採用されています。アナログレコードのカッティングでは、MFB(機械的NFB)を掛けないとレコード原盤ができないのでした。学問的には、ボーデやナイキストにより、NFBの安定動作についての考察がかなりなされてきて、現在も、これらの理論での検討結果でNFBの動作確認しています。
一方、そのような面倒なことはやめて、NFBなしにしようとすると、真空管アンプでは、それは簡単に実現できますが、まず、NFBを掛けないと、残留ノイズで、ノイズが音楽を邪魔して、楽しむことが難しくなります。よく、NFBを掛けるとS/N比が改善されると、オーディオエンジニアやオーディオ評論家に間違った認識があるようですが、S/N比はNFBのありなし、NFB量で変動することはありません。なぜなら、NFBを掛けるとその分ゲインが減るので、S/N比は変わらないのです。ノイズは、NFBを掛けると残留ノイズレベルが下がるので、リスニング時の妨げにならないのです。
逆に言えば、効率の低いスピーカをお使いならば、ノイズレベルは聴えにくくなるので、NFBは掛けなくともノイズの面からは問題はありません。ひすみ改善、DF(ダンピングファクター)については別として。
いよいよ、オーディオを充分楽しめる季節になりました。
パッシブプリアンプは、MASTERSのアンプカテゴリーのなかで、発売以来ずっとご好評をいただいております。
最近は、バランス仕様のご注文も多くなってきました。
それも、皆様がバランス伝送の意味を理解されるようになっていただけてきたからのように感じます。つまり、バランス仕様のパッシブプリアンプでアンバランス(RCA)入力の場合、その信号をバランス信号のHOT側と理解して、HOT側を音量調整して、アンバランス入力の場合でもバランス仕様でコンパチブルできるということです。そうなると、アンバランス信号をバランス変換する高価なトランスを内蔵しなくても済み、価格セーブにつながります。
最近ご購入いただいたお客様からは、先日購入したMASTERSのトランス式パッシブプリアンプを聴いて、“再生帯域の広さ、腰高にならない、低域の伸び、ほれぼれとさせる高域があると思う。”といった感想を頂いております。
このお客様は、なんと、30年間に12台のプリアンプを使ったというベテランであり、音のグルメといえましょう。
“通常の擦動式ボリュームでは「到達できない部分がある」と感じる”という感想も頂きました。
さらに、複数のカスタム仕様でのご注文をいただき、現在設計中です。
本日発送した“MASTERS CA-999S/A CUSTOM”では、入力を1系統のみでシンプルにして、よりピュアサウンドを求める方に向いたカスタム仕様としました。このパッシブプリアンプを発送前のエージングで聴いていたところ、そのパワフルでのびのびした低域・中低域には、製作者の私ですら、少なからずびっくりしました。決して製作者の自己陶酔ではないと思います。