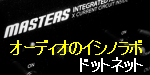猛暑、酷暑の夏も終り、やっと音楽を聴きたい季節になってきました。
オーディオ趣味はこのところとてもオーディオリターナが増えてききました。そのタイプには2つあります。
1つ目のタイプは、長らくオーディオを休んでいた方が目覚めて、しまってあったオーディオ装置を取り出して楽しもうとする方々です。オーディオ装置は電気機械ですから長らく電源を入れていないと、ことにアンプがうまく動いてくれないトラブルが多いようです。クルマと同じで機械はなるべく短時間でよいですから週1回は動かしてやるのが良いです。
もう1つのタイプは、オークションでかつての銘機を入手した方々です。それを動かしてみると、うまく動いてくれないことも多いようです。オークションは原則としてノークレーム、ノーリターンですから返すわけにもいかず、修理依頼するしかないのです。イシノラボ/マスターズにはこのようなケースと思われる修理依頼がけっこうあります。
何分にも古い年代の機械なので交換パーツ、とりわけスイッチ、ボリュームの不良は困ってしまいます。最悪、これらのパーツを分解修理することになりますから、多くの修理時間を費やし、また、うまくなおるか?というリスクを伴います。
このような事態を少しでも回避するには、マスターボリュームならラウドネスコントロールの使用をあきらめてもらえれば、代替ボリュームの入手はでき、費用もそれほどかかりません。また、スイッチ動作でノイズが出るとすれば、スイッチを動かさず、そのままにして使えばこれもコストセーブになります。
要は症状によってユーザーさんの思い切りでコストセーブで銘機を使えることができるのです。過去の銘機を完璧に直すことは老人に若い時と同じような元気さを要求するようなもので、熟年にふさわしい使い方をすればまだまだ4-5年は使えるのです。
どうぞ、修理のご相談ご依頼は上記の内容を理解いただいた上でお願い致します。
|
ブログのホーム |
次ページへ |
最近のオーディオ製品の高額化には、ため息をつくばかりです。その根拠には、原材料の大幅な高騰(銅・ステンレス・樹脂材料は4倍、鉄は2倍以上など)があるものの、値上がり分を超えた高い値付けには驚きます。メーカーさんに気を使うオーディオ評論家さんの心ある方々は、オーディオ誌で、“数が出ないから、高くする。ますます、売れなくなる。これでは悪循環になる”と述べております。海外では、オーディオ趣味は超お金持ちの道楽になって、¥500万とか、¥1,000万とかの超高額オーディオ製品が主流になっています。
少なくとも日本では、オーディオ製品は手の届くものにしておくべきです。皆様は、老後の不安を抱えて、蓄えをある程度持っておられると思います。それを取り崩して、オーディオ趣味につぎ込むのは先々心配です。オーディオ趣味は、生活を脅かさない健全な趣味であるべきとマスターズ/イシノラボは考えます。
当社では、ネット販売をメインとして、流通経費(20-25%)をセーブしております。更に、利益を蓄積して、規模を大きくして、商売することはあまり考えておりませんので、ぎりぎりの価格にしております。ユーザー様からは、“驚くほどの、中身の濃さ、音質の良さ!”とコメントをいただいております。
ネットビジネスの問題点は、製品の説明、画像からしか情報をつかむことしかできないことです。“触ってみる”、“聴いてみる”ということができませんので、まず当社を信用していただけることが重要と考えています。しかし、サウンドは、料理のように、皆様の嗜好がございますので、当社でおいしいと確信しても、お耳に合わない場合もございます。その場合は、どうぞ、クリーングオフの制度で遠慮なくご返品ください。当方はオーディオ界、40年以上のキャリアですので、皆様のお気持ちは充分理解できます。
以上、ご理解のうえ、よろしくお願い致します。
私は元々、人間好きなせいか、人間心理については昔から興味をもっていたものです。ゼミも、エレクトロニクスの傍ら、進んで別の心理学の先生の指導も受けました。
その関連で、1970年代前半に、一時はやった4chステレオ開発においては、私なりに、特に音の方向性の認知の音響心理実験を随分とやったことを思い出します。
当時は、2chステレオではオーディオ熱が凄かったですから、オーディオの音質評価に関して、計量心理学の手法で、何とか音質の差異を、統計学でいう「有意差」に持ち込もうと、1970年代、オーディオ各社は音響心理の研究を始めました。東芝の厨川さん、松下、日立の中山グループ、などなど。NHK技研も二階堂さんが先頭をきってアクティブに研究していました。
私が在籍していた当時のサンスイでは、各設計グループで、音質検討し、その結果、音質にかかわる設計の配慮をしておりました。
ところが、1975年あたり、オーディオ誌での評論家の音質記事が売れ行きに影響すると考えた経営者は、急に、社内に音質評価委員会なるものを設置したのです。(これは私のつたない連載「日本オーディオ史」のはじめのあたりに記述してあります。)
どうするかと見ていると、同じ音量レベルにして、一対比較法によって、合格・不合格を音質評価委員が下すようになったのです。
こうなると、評価者にとってかなりのストレスになり、短時間の比較はまず無理なことだと、私は思っていました。その結果、出てきた製品の音質は個性のない、魅力のないものになってしまいました。1976年になって、この委員会は廃止され、音質を担当する人間が外部の有識者との意見を考慮しつつ、ブランドの音質を維持・向上してきた経緯があります。手法として、ブラインド・一対比較は避けて、じっくり、聴きこみ、聴き取った感触を確信になるまで、とことん、追い込んだ記憶が蘇ってきます。
最近でも、オーディオマイスター制度を取り入れて、上記の方法を採っている会社もありますが、メーカーという立場があり、ハイエンド・オーディオは我々のようなスモールスケール工房のほうが適性があるように感じています。
また、やはり、オーディオ趣味は、主として西洋音楽を聴く楽しみであるから、センスと音楽的素養は必要と思います。
ちなみに西洋人は、自分達の音楽であるから、ごく自然に評価できるのだと思います。サンスイ当時、イギリスから、評論家マーチン・コラムス氏を招いて、指導を受けたのを懐かしく思います。彼等は石作りの家の伝統から、響きを大事にするし、まず、基本は低音、それも低音の少し上の中低音がリッチであることを重視します。
私も、まず、アンプの中低域の充実さを重視します。それから全体のサウンドバランス、透明感、広がり、弾力性などを改善しつつ整えることをやっております。
エンジニアリングと感性の狭間がオーディオです。これは、ある意味ではオーディオ技術は工芸の域になっているとも言えましょう。裏返せば、科学が解明できないことが、いっぱい、沢山、膨大にあり、そこにヒューマンファクターがキーになるのだと思っています。
|
ブログのホーム |
次ページへ |