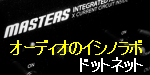コロナ禍とオーディオ
東京オリ・パラ五輪が終わって、ようやく感染者のピークを越えました。
そして、予測を超えるペースで感染者が激減しています。
その理由は医療関係者、有識者の方も説明できません。
もちろん、ワクチン接種が進んだとしても、それだけでは説明できないです。
そして、第6波が11月頃から発生するかも知れません。
それはそれとして、オーディオは引きこもり趣味・道楽であるので、それほど変化はないようですが、さあどうなるのでしょうか?
マスターズアンプ
つい先日、特別ご提供品 プリメインアンプ“MASTERS AU-600/JBL・Limited”の1台目が売り上げとなりました。
とても良いお買い物をされたとひそかに思っています。
画面では良くわかりませんが、2mm厚のアクリルプレートでフロントパネルを仕上げた姿はとても美しく、美しいサウンドです。
ご希望があれば、あと2台分のキーパーツがあります。
山水のXバランス増幅回路
山水在籍当時、私が提唱したバランス増幅回路ですが、αシリーズ以降は山水を退いて、私は会社を設立、そちらのほうに没頭していたので、実態は故 横手さんに時たま聞く程度でした。
それから20数年の時が流れ、山水は消滅してしまいました。
けれども、オークション、中古市場では人気があり、その関係もあって、マスターズに修理依頼が少なくありません。
多くは、スイッチ・ボリューム関係の接触不良です。次は、プロテクションが誤動作して使えないという不具合です。
山水のXバランス増幅回路は2組の差動プッシュプル回路でバランス出力を作り出しています。そして、ファイナル段に供給する電源は、グランドに関係ないフローティングとなっていますから、パワーアンプの場合、その出力はグランドには関係なく、出力のホット/コールド間がスピーカーを動作させるようになっています。
したがって、対グランド電位は特に決まりませんが、差動プッシュプルのエミッタ抵抗を可変することによって、グランド電位に近づけることができます。
一旦、製造時に設定すれば安定し、スピーカーをドライブします。
ところが、20年以上の年月を経ると、バランス増幅変換回路のDC電位が返送して、プロテクションが動作して、音が出なくなるトラブルが出ることがあります。
XバランスはDC電位がいかに変動しようと、アンプ出力のHOT/COLD間で±30mV以内であれば、まったく問題なく動作します。
そこで、対グランド電位が±4V以上くらいで、プロテクションが動作するようになっています。これが、このトラブルの原因の一つです。
このプロテクション回路をはずせば、直るはずです。
そうはしなくとも、30年以上の経年変化した半固定ボリューム(2個)を交換したら、周囲のプリント基板のハンダが劣化しているので、これらを修復して直ることがあります。
なお、マスターズのZバランス回路は原理的には似ておりますが、2段差動バランス増幅(Xシリーズは3段バランス増幅)構成ですので、DC電位的にも安定し、NFB量も少なく、位相補償コンデンサーはわずか3PF1個だけで超安定、かつ、電源ON時のショックノイズも発生せず、SPリレーが削除でき、より高音質です。
アナログレコードとコンサートサウンド
少なくともセッション録音では、マイクは楽器に近接していますから、リスナーがコンサートホールで聴くより、より近接(生々しい)音が録れています。
このようなサウンドをアナログレコード時代は夢中になって聴いていたのです。
良く言えば、コンサートサウンドを超えたサウンドを楽しんでいたのです。そのあたりで、ああだ、こうだという面白さで、オーディオ評論家が誕生したともいえます。
かつて、究極のアナログ録音として、ダイレクトカット録音がシェフィールド等のレーベルで評判になりました。
近接マイクで取ったジャズ“テルマ・ヒューストン”は売り切れ完売になりましたが、コンサートホールで2マイクロホン(20mくらいの距離)で録ったダイレクトサウンドレコードは、あまり売れませんでした。
要は、オーディオファンはコンサートホールでは聴けないサウンドを聴きたがっていたのです。
したがって、デジタルサウンドのCDはAC/DC/AC変換過程で、このフレッシュさを失っていました(但し75分の収録時間は便利)。
だから、アナログレコードが復活してきたのです。
もちろん、SACDのような高品位CDサウンドは良いだろうと思えますが、採算的にセッション録音はできないのが残念です。
過去のカラヤン、バーンステイン等の名盤はすべてセッション録音です。